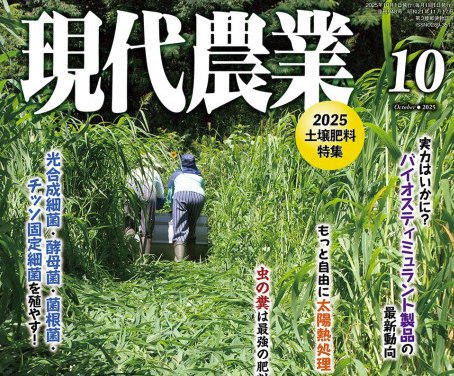第8回WS2日目 in 美幌町
- Yoshiharu Seo

- 2025年7月4日
- 読了時間: 2分
大地再生の旅第8回ワークショップ2日目、小清水町から50分ほど移動した美幌町の池端さんの畑です。

最初の写真は、昨年9月にマオイFALLミックスを播種し、一列だけすき込まない試験をされた畑(写真下)。今年の夏のカバークロップでは、秋にすき込まない試験をより広い面積で実践してみることになりそうです。

写真上の状態で、寒さで枯れて終わる種や、枯れずに雪の下になったあと、翌春に生長をはじめるへアリーベッチやナタネなどがミックスされたFALLミックス。この畑は、春先に心配された土の乾き方は起こした畑よりも良く、寒さで枯れた植物残渣も、生き残ったへアリーベッチやナタネも浅い耕起を1回行うことで、春の植え付けができたということです。

カバークロップによる団粒構造により、春先は土が軟らかく、水はけもよかったそうですが、春の大雨で、写真上(2番目)の右側にある水路へ畑全体の表土が流されてしまったそうです。有機物は軽いので、大雨で最初に流されるのは有機物です。そして、表土を流されると、細かなシルトなどがクラスト状になり、水や空気の流れを悪くしてしまうことになります。

もし、この畑全体のカバークロップを秋に処理せず、春まで放置し、植え付け3週間までにできるだけ浅く耕して、次のタマネギ苗の定植ができたとしたら。同じような大雨が降ったとしても、その水を土の中に貯めこむことができ、表土が流されるリスクも最小限に抑えることができるのかが、今後のテーマです。大雨による土の流亡を軽減できるかという実験は、他のメンバーにとっても重要な課題です。
下の写真は、育苗ハウスのカバークロップです。施設栽培の土壌の健康を、次の作までの間に、回復させる手法としても注目されています。

こうした一つひとつの取り組みが共有されて、大地再生の旅は、一歩ずつ前に進むことができます。