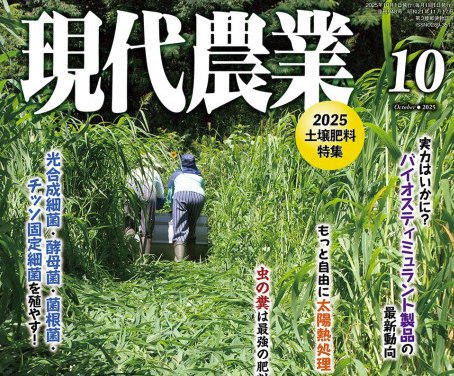第8回ワークショップin十勝
- Yoshiharu Seo

- 2025年7月3日
- 読了時間: 2分
大地再生の旅(MRJ)第8回ワークショップの1日目は十勝地方初となる音更町で開催しました。音更には第1期、第2期のメンバーがいることもあり、カバークロップや不耕起への取り組みに関心が高まっています。
十勝のメンバーだけでなく、オホーツクから、札幌、洞爺湖町、道外からは東京、福島県からもMRJのメンバーが参加してくれました。そして、メンバーが声をかけてくれた知り合いの農家さんや研究者の方々など、多くの方が参加していただきました。

国内では、まだまだ実践者が少ない不耕起、カバークロップの挑戦において、課題が山積していることは、農家さんが一番わかっていますが、毎年毎年多くの知見を共有して学びあえているのがMRJのすばらしいところだと思っています。

まずは、土を掘ってみる。そして、葉の糖度を測ったり、根粒菌の活性を見たり、透水性テストをしたり、土壌診断をしてみると、期待していた数値や結果ではないこともあるので、落ち込むこともあります。

カバークロップで畑の土を改善しようとしても、カバークロップ自体の生長が期待していた生育がないこともあります。そのときのチェックポイントは、土壌の圧縮や空気や水の入る空隙などの物理性の問題もあります。ただし、これをロータリーやプラウで土を壊してしまうと、一時的な軟らかさを得られるだけで、土は益々硬く締まっていくことになります。こうした対策には、カバークロップと同時に、時にはサブソイラーやバイオスティミュラントを使って根の生長を助けてあげることも必要になることなどを土を見たり、触れたりすることで対策を話し合いました。

「失敗しないということは、何もチャレンジしていないということ」というレイモンドさんの言葉がみんなのチャレンジへの姿勢を後押ししてくれました。

後半の2時間は、JA音更町の大会議室をお借りして、座学と質疑応答、そして、ワークショップに参加していただいたみなさんの感想(ピークモーメント)を共有しました。